便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
第41号 行為計算否認規定の新しい可能性 
~ヤフー事件控訴審判決※1 ~
文献番号 2015WLJCC002
京都大学 教授
岡村 忠生
1.問題の所在 — 法人税法132条の2と経済的観察法
法人税法(以下「法」という。)132条の2は、合併、分割などの組織行為を行う法人とその株主の法人税につき更正・決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準などの額を計算することができると規定している。この規定は、租税回避の否認規定と考えられてきた。租税回避の否認とは、納税者の選択した法律関係(私法上の契約関係など)が、課税要件を設けるにあたって前提とされた通常の法律関係とは異なる異常なものでありながら、通常の法律関係を選択したときとほぼ同一の経済的成果を獲得し、かつ、通常の法律関係に結びつけられた納税義務を排除または軽減する場合(租税回避)、納税者の形成した実際の法律関係ではなく、通常の法律関係が形成されたものと擬制して課税を行うことをいう。しかし、以下に見るように、本件の課税処分は、租税回避の否認では説明することができないと思われる。
これに対して、ドイツには、経済的観察法という考え方があり※2、1919年から1977年まで実定法にその規定が存在した。経済的観察法は、①租税法の解釈と、②事実認定を、租税法の目的や国民観(ナチス期には国家社会主義的世界観)に基づいて行う原則である。本件の課税処分は、法132条の2を、①に類似する形で適用したものではないだろうか。
2.事案の概要
X(原告、控訴人)は、訴外SB社に株式の約42%、米国法人Y社に35%を所有された上場法人で、I氏(SB社取締役)を代表取締役社長、S氏(SB社代表取締役社長)を取締役会長とし、インターネットサービス事業を営んでいた。SB社は、2005年2月に、訴外英国法人K社グループから訴外CS社の株式全部を譲り受け、完全子会社とした。CS社はデータセンター事業を営み、2007年3月期以降は毎年20億円程度の利益を上げるようにはなったが、2006年3月期までの繰越欠損金額が総額で約666億円存在し、うち124億円は2009年3月末で期限切れとなるものであった。このような事情を背景に、以下の行為が行われた。
- ⅰ) 2008年12月26日、I氏はCS社副社長に就任。
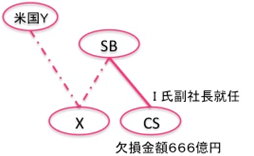
- ⅱ) 2009年2月2日、CS社は、非適格分社型分割によりCF社を設立。
CF社は、資産調整勘定100億円(後年度に損金算入)を計上。
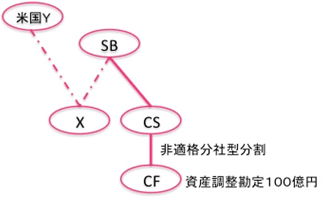
- ⅲ) 同月20日、CS社は、Xに対して、CF社株式の全部を115億円で譲渡。
これにより、CS社とCF社の間の完全支配関係が消滅。
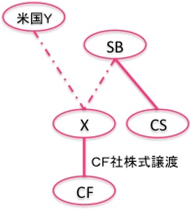
- ⅳ) 同月24日、SB社は、Xに対して、CS社株式の全部を450億円で譲渡(「本件買収」という。)。
これにより、XとCS社の間に特定資本関係※3が発生。

- ⅴ) 3月30日、Xは、CS社を適格合併(「本件合併」という。)により吸収し、未処理欠損金額543億円を引き継ぐ。
この引継ぎのためには、みなし共同事業要件(法57条3項)が充足されねばならず、そのためには、I氏がCS社の特定役員
(当時の法人税法施行令(以下「令」という。)112条7項5号)であることが必要であった。
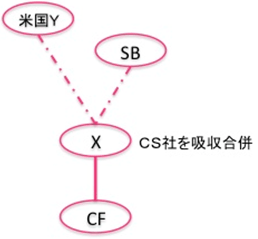
課税庁は、法132条の2に基づき、Xに対してCS社の欠損金の損金算入を否認する処分を、CF社に対して資産調整勘定の損金算入を否認する処分を行った※4。XとCS社は、処分に対して審査請求を経て訴訟を起こした。本稿では、Xに係るものを取り上げる。
第1審東京地裁は、Xの請求を棄却した※5。判決は、法132条の2が設けられた趣旨は、組織再編成の形態や方法は複雑かつ多様で同じ経済的効果を発生させ得る複数の方法があり、これに対して異なる課税を行うこととすれば、租税回避の温床を作りかねないという点にあるから、法132条の2が定める「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、(ⅰ)法132条(同族会社の行為計算否認規定)と同様に、取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか、(ⅱ)組織再編成に係る行為の一部が、組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し、当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの、当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものを含むと判示した。そして、組織再編成を構成する個々の行為について個別にみると事業目的がないとはいえないような場合であっても、組織再編成全体としてみた場合に組織再編税制の趣旨・目的に明らかに反し、又は個々の行為を規律する個別規定の趣旨・目的に明らかに反するときは、上記(ⅱ)に該当するとし、同条の適用対象を、通常用いられない異常な法形式を選択した租税回避行為のみに限定することは当を得ないと判示した。
欠損金の引継ぎが認められる理由を支配の継続に求め、特定役員引継要件は、これに形式的に該当する場合であっても、それにより課税上の効果を生じさせることが明らかに不当であるという状況が生じる可能性があることを前提に規定されたものであり、組織再編成に係る他の具体的な事情を総合考慮すると、合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているとはいえず、同号の趣旨・目的に明らかに反すると認められるときは、法132条の2の規定に基づき、特定役員への就任を否認することができるとした。そして、本件における諸事情を総合勘案すると、本件副社長就任は、特定役員引継要件を形式的に充足するものではあるものの、それによる税負担減少効果を容認することは、特定役員引継要件を定めた令112条7項5号が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであり、また、本件副社長就任を含む組織再編行為全体をみても、法57条3項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるということができるので、本件副社長就任は、法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当すると述べた。
3.控訴審判決
東京高裁は、Xの控訴を棄却した※6。判決理由は、基本的には原審と同じである。ただし、欠損金の引継ぎが認められる趣旨が、原審における支配の継続から、共同事業の継続(「経営面からみて、合併後も共同で事業が営まれているとみることができるという考え方」)に改められた。判決は、この考え方に基づき、I氏のCS社副社長就任に関して、就任が特定資本関係発生の約2か月前、SB社においてCS社の株式譲渡・合併を行う方針を決定した約1か月後であったこと、I氏の具体的な職務内容が本件買収・本件合併後の事業計画に係る業務か本件買収・本件合併の準備に係る業務に限られていたこと、取締役副社長としては非常勤であり、代表権、部下や専任の担当業務はなく、役員報酬も受けていないことなどの事実から、「本件副社長就任の目的が専ら控訴人の法人税の負担を減少させるという税務上の効果を発生させることにあると認められ、仮に上記目的以外の事業上の目的が全くないとはいえないものと認定する余地があるとしても、その主たる目的が、控訴人の法人税の負担を減少させるという税務上の効果を発生させることにあったことが明らかであると認められる」と述べ、I氏が「本件合併時にその取締役副社長であることによっても、・・・合併後も共同で事業が営まれているとは認められず、CS社の上記未処理欠損金をXの欠損金とみなしてその損金に算入することは、法57条3項及び令112条7項5号が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであると認められる。」と判示した。
4.行為計算否認規定の新しい可能性
この事件の課税処分とそれを認めた原審および控訴審の判決は、冒頭でも述べたように、これまで租税回避の否認と考えられてきたものとは異なる。なぜなら、本件課税処分はI氏のCS社副社長就任という事実を最初からなかったものとして課税関係を形成しているのではなく、その事実の存在を認識した上で、これに対する課税上の評価として、就任の期間や目的、役員としての業務内容が共同事業の継続という欠損金引継ぎを認める法の趣旨目的に合致しないため、欠損金引継ぎを認めることが「不当に税負担を減少させる」との判断を行い、当該規定の適用を認めなかったと考えられるからである。副社長就任が課税要件との関係で異常であったかどうかは問題とされていないし(吸収合併する相手会社に役員を送り込むことは、通常行われている。)、事業上の目的が一定程度存在していたことは、判決も認めている。そうすると、この事件における行為計算否認規定の適用は、この規定の新しい可能性を開いたことになる。
本件での行為計算否認規定の適用のあり方は、どちらかといえば、経済的観察法の①に近いものであろう。本件のような法の解釈、すなわち、納税者に有利な規定について、厳格な文言解釈を緩和し、限定的に解釈することは、従来、行為計算否認規定の「助け」を借りずに行われてきた。しかし、本件のように行為計算否認規定を「媒介」させることで、限定解釈できる範囲は大きく広がるものと思われる。本件は上告中であるが、果たして、法132条の2に、このような作用を認めることが適切かどうか、最高裁の法律審としての判断が待たれる。もし、経済的観察法のような適用を認めるのであれば、憲法の求める自由で平等な社会において、租税法を通じた解釈の原理は何か(ナチス的国家主義・全体主義ではないはずである。)、税負担軽減行為(タックス・プラニング)がどこまで認められるかが、問われることとなろう。
この事件の原審判決の約2ヶ月後、IBM事件東京地裁判決が下され、納税者が勝訴した※7。現在、控訴審で係争中である。この事件でも損失控除が問題となったが、そこでの損失は、本件のように事業の中で生じた経済的実質のある損失の控除ではなく、自社株取得に伴うみなし配当課税により、株式譲渡損失として生じる計算上のものであり、連結納税を利用してグループの他の法人の利益を相殺するために用いられた。また、この自社株取得の相手方となった原告法人(持株会社)は、日本では納税義務者(有限会社)であるが、米国税制上は納税義務者ではないハイブリッド・エンティティーとされていた。このスキームは、綿密に計画されたものであり、課税処分に対しても、迅速で周到な対応が行われたと伝えられている※8。IBM事件は、国際的なタックス・プラニングの例といえる。本判決は法132条の2に新しい可能性を見出したが、連結納税に関する同法132条の3も同じように使えるかどうか、IBM事件控訴審においては、国がこの規定を適用することも考えられる。それによって国が勝訴できれば、これらの行為計算否認規定は、いわば「日本版・経済的観察法」の規定と位置づけられることになろう。
- 東京高判平成26年11月5日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA11056001。評釈として、太田洋「ヤフー事件控訴審判決の分析と検討」税務弘報2015年3月号掲載予定がある。原審判決は、東京地判平成26年3月18日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA03188002である。また、同日に同じく東京地裁により下された関連事件〔IDCF事件〕の判決、東京地判平成26年3月18日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA03188001も参照。これら2つの東京地裁判決について、岡村忠生「組織再編成と行為計算否認(1)」税研177号73頁(2014年)、「同(2)」税研179号73頁(2015年)参照。
- 清永敬次『租税回避の研究』(ミネルヴァ書房、1995年)第1編、岩崎政明「租税法における経済的観察法 : ドイツにおける成立と発展」筑波法政5号30頁(1982年)参照。
- 事件当時の法人税法において欠損金を引き継ぐための要件の1つ。現行法では支配関係。
- この処分が争われたのが、IDCF事件である。本件と同日の東京地判平成26年3月18日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA03188001参照。
- 東京地判平成26年3月18日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA03188002。
- 東京高判平成26年11月5日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA11056001。
- 東京地判平成26年5月9日Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA05096002。解説として、髙橋祐介・ジュリ1473号8頁(2014年)参照。
- 朝日新聞平成26年5月10日朝刊37面。日本経済新聞平成26年5月29日朝刊。
(掲載日 2015年1月13日)