
- 判例コラム臨時号: 日本大学大学院法務研究科 客員教授 前田 雅英「警察官を騙して捜査活動を行わせる行為と偽計業務妨害罪」
- 判例コラム臨時号: 青山学院大学法務研究科(法科大学院) 教授 弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士 浜辺 陽一郎「疑われる取引回避がベターであることに変わりなし」
- 今週の判例コラム: 中央大学法科大学院 教授 佐藤 信行「携帯電話とカーナビのワンセグ機能はNHK受信契約を導くか」
- Joint Seminar by IPBA & JIDRC
- 新企画【プレミアム・セミナー】アンダーソン・毛利・友常法律事務所&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー
- 掲載記事:日本法総合オンラインサービス『Westlaw Japan』が『旬刊商事法務』をオンラインで提供
- [プレスリリース]日本法総合オンラインサービス『Westlaw Japan』が『旬刊商事法務』をオンラインで提供
- 【不具合解消しました】日本製品<Westlaw Japan>モバイルアプリの不具合について(2019年5月23日)
- 【最新収録状況 令和元年11月7日】 ≪判例≫≪法令≫ ≪判例タイムズ1464号≫ ≪時の法令「法令解説」2083号≫ ≪NBL1157号≫更新しました。
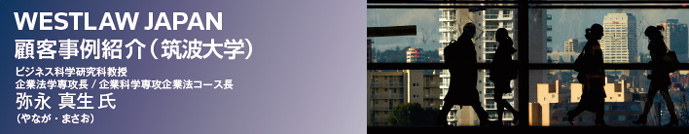 ビジネス科学研究科教授 企業法学専攻長/ 企業科学専攻企業法コース長 弥永 真生氏
ビジネス科学研究科教授 企業法学専攻長/ 企業科学専攻企業法コース長 弥永 真生氏
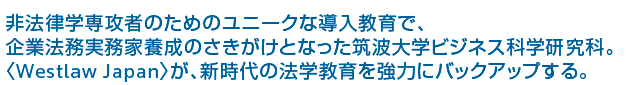 非法律学専攻者のためのユニークな導入教育で、企業法務実務家養成のさきがけとなった筑波大学ビジネス科学研究科。〈Westlaw Japan〉が、新時代の法学教育を強力にバックアップする。
非法律学専攻者のためのユニークな導入教育で、企業法務実務家養成のさきがけとなった筑波大学ビジネス科学研究科。〈Westlaw Japan〉が、新時代の法学教育を強力にバックアップする。
― 先生は他の学問を修められてから法律学の世界に入られ、いわば外からアプローチされたというご経験をお持ちです。今でこそ法律学の学習方法やリサーチの体系化は珍しくありませんが、先生が『法律学習マニュアル』(有斐閣、2001年)を刊行された当時は非常に斬新で、法学教育の世界に衝撃を与えました。
経済学部を卒業して法学部に学士入学したとき、大きなカルチャーショックを受けたのを、今でもはっきりと覚えています。「民集」「判時」「判タ」などという言葉が飛び交っていて、いったいどんな意味かがわからない。先生の話は日本語として聞こえますが、どこが重要なのかが全くわからない。棄却と却下はどう違うのか、事件番号とは何なのか。どうやって文献を調べ、理解し、レポートにまとめたらいいのか、皆目わかりませんでした。経済学では理論がわかれば、理解としてはそれで十分なのですが、法律学では条文の理解だけでなく、「解釈」というものが存在するというのも大変な驚きでした。つまり、私は「法律学の暗黙知」をまったく知らなかったのです。
1990年に筑波大学大学院の企業法学専攻が発足し、修士課程では法学部以外の出身者に法学教育を行うことになり、実際に法学部出身でない院生が三分の二を占めました。私もスタッフの一員として教育にあたりましたが、文献検索と法文書作成を行う入門的科目として開設された「法文献学」の担当を私が引き継ぐにあたって、法律学に必要な知識をシステマティックに学生に伝えたいと考えました。今でこそ、〈Westlaw Japan〉をはじめとするデータベース検索が可能ですが、20年前はほとんど紙ベースの資料しかなく、資料索引も少なく、検索そのものが一苦労だった時代です。
そんな状況の中で教育手法を考えたり、資料をまとめるうちに「法律学の導入教育として体系立てるべきだ」と確信するに至りました。そんな話を聞いた有斐閣の雑誌編集部が『法学教室』への連載を薦めてくれたことをきっかけに、『法律学習マニュアル』としてリサーチ教育をはじめとした法学の「学びの方法」を体系化したのです。
いまだ十分でない判例情報の公開
― 言葉の意味や資料の所在のわかりにくさだけではなく、法律の世界独特の「お作法」も、初学者にとっては高いハードルですね。
法律論文で判例を引用する際には、公式判例集である民集(『最高裁判所民事判例集』)にあれば、まずそれを出典として挙げるべきで、ないときは判時(『判例時報』)、判夕(『判例タイムズ』)の順で引用する、という「暗黙のルール」があります。「民集にあるのにそこから引用しないのは、“勉強が十分ではない”という印象を与えるから、必ずチェックしなさい」と学生に教えますが、別にそれはルールとして書かれているわけではなく、職人芸のように伝えられているのです。
判例解説や評釈の引用の仕方にも優先順位があって、最高裁判所調査官が書いた『最高裁判所判例解説』(法曹会)は、もともと雑誌『法曹時報』の記事に加筆されたものですが、それ以前に短い速報的な記事が『ジュリスト』の「時の判例」欄に載ることがあります。最近の最高裁の判決についてレポートや論文を書く場合には、まず『ジュリスト』を見て、『法曹時報』『最高裁判所判例解説』の順にチェックする。引用は公式性の高い逆の順番で行う……このような、明示的に教えられてこなかったノウハウを最初に学生にまとめて教えてしまい、その先の議論にエネルギーを使うのが院生の成長と法律学の進歩に通じると考えたのです。
―データベースが普及して判例検索の方法が様変わりした現在でも、判例集の「縦割り状態」はまだ続いています。
わが国は判例法の国ではないということもあり、われわれ研究者が必要とする判例が出てくる仕組みには必ずしもなっておらず、裁判所自体も自ら下した判決の重要性を必ずしも理解していません。一方で、その評価をすべき立場である判例雑誌の出版社側にも、判例を使いやすく加工し、提供する意欲が乏しいと言わざるを得ません。アメリカでは、Westlaw の前身である出版社のWest が公式判例集を出していたという歴史的経緯もあり、判決文は即公開され、キーワードが網羅的に付与され検索可能に加工されて、あらゆるニーズに対応しています。
― 現在、知財や医療過誤事件の判決はすべて裁判所ウェブサイトで公開する方針と聞きましたが、一般の裁判例については各裁判所でチョイスされたものが公開されているようです。
当事者が公開したくないと思う裁判例は出ない傾向にあります。マスメディアで大きく報道される事件を「著名事件」と呼びますが、これらの判決文を入手するすべも限られています。そもそも、判決文を読んだだけでは、当事者が何を争ったのかのはわからないのです。
―それは、どういうことですか?
判決文は裁判官の取捨選択でできています。法律論は丁寧にできていますが、事実認定は裁判所が当事者の主張をピックアップし、組み立てたものに過ぎません。ですから、「生の事実」が判決文に書かれているわけではないのです。裁判記録には当事者がどういう主張をしたか明確に書かれていますが、これにアクセスするのも一苦労です。
判決確定後は地裁で見せてもらえますが、控訴されると閲覧不可能になってしまいます。近年、実務ではスピード感がより強く求められ、会社法分野の事件などでは同時進行で素早い分析が求められますが、研究者も強くアピールしないからか、ニーズが高いと認識されていないのは問題です。それでも研究者は代理人弁護士に依頼したり、意見書を求められる機会に判決文や記録を入手することができますが、そうでない大多数の人にとってはアクセスのすべがありません。日本では「判例は公共物である」という意識が非常に低く、大きな問題です。
裁判が最後どうなったのかもよくわからない仕組みになっているのも問題です。最高裁に上告後、上告不受理となったのか、それとも上告棄却なのか。最高裁が実体的判断をしたかどうかで大きく意味合いが異なるのですが、どうなったかが全くわからないのです。裁判所ウェブサイトや判例雑誌に載るのは破棄自判や差し戻しなどごく一部で、大部分は掲載されないため、裁判がどんな決着を見たのかがわかりません。せめて高裁、最高裁でどのように結論づけられたのかを追えるようにするべきでしょう。
会社法研究の観点からいえば、裁判所の決定が公開されないのも痛手です。さらに裁判は、判決よりも和解で終わることが圧倒的に多いのですが、そうなると当事者間で守秘義務契約が交わされることが多く、和解内容が明らかになりません。事件がどんな帰結をたどったのかが追跡不能になってしまうのです。そもそも、事件番号がわからないと探しようがない、裁判の結末がわからないとなすすべがないなど、今の日本の裁判所には、このような情報公開の壁が依然として存在しており、実証分析に基づく研究が立ち後れている大きな理由のひとつです。
〈Westlaw Japan〉ならではの機能を、新しい法学教育に活用
―いまだ十分とはいえない判例情報の公開状況ですが、データベースはどのような役割を果たしているでしょうか。
会社法領域では、判例集に載らない裁判例が非常に多いのですが、〈Westlaw Japan〉の判例データベースは、判決文の収録スピードが他に比べて圧倒的に速く、また網羅性においても他の追随を許しません。判例集などの公刊物に載らない判決文を独自に入手して掲載する努力は高く評価できます。学生には「法令と判例については、大学で導入しているデータベースの中で、まず〈Westlaw Japan〉で検索しなさい」と教えています。
〈Westlaw Japan〉の機能としては、「参照条文」を最も活用しています。「判例はどのように動いてきたか」を学生に理解してもらうには、全体の流れの中に判決がどう位置づけられるのかを知ることが重要です。判決文に引用した判例が明示されているならいいのですが、そうでない場合がたくさんあります。その場合は、参照条文から関係する判例を引き抜いてくる面倒な作業が必要でしたが、データベースならではの全文検索を組み合わせることで、漏れなく検索できるようになりました。このようにデータベースの使い勝手が向上することで、研究者が参照する判例雑誌も、それまでの権威による序列が崩れ、データベース対応に優れた雑誌がよく参照されるようになる「逆転現象」も起きているようです。
―いわゆるビジネスロー分野は大きく育ち、企業法務担当者も増加しました。これらを見据え、これからの法学教育はどのように展開すべきでしょうか。
求められているのは、必要な情報を適切に見つける能力と、それを理解する能力を身につけることです。新司法試験を受けるためには知識を自分の中に定着させることが必要ですが、実務に役立つ教育としては、必要な情報を的確に早く見つけ、「どう正確に読み込むか」そして、それを「理解できる能力」へと、学習の軸足を移すように法学教育は転換されるべきでしょう。日本の法律系データベースは―特に判例で顕著ですが―20年前には考えられないほどの進歩を見せました。過去を振り返ると、「贅沢になったものだ」と思います。法令データベースについても現行法規が網羅されているのはもちろん、いわゆる旧法令についても、「ある特定の日に施行されていた法律を見る」など、データベースでなければ実現できない機能が非常に充実しています。今後は論文や文献など二次資料の収録を充実させて検索可能とし、肝心なスキルである「読む・分析する」ことに学生が集中できるような環境が整えられると、なお素晴らしいと思っています。

ビジネス科学研究科教授 企業法学専攻長/
企業科学専攻企業法コース長
弥永 真生 氏
東京大学助手を経て筑波大学社会科学系講師・ 助教授を経て現職。東大在学中に司法試験、公認 会計士第三次試験に合格。複数の専門を生かした 研究を行い、論文や著書を多数執筆。『演習会社 法(第二版)』(有斐閣)など。








